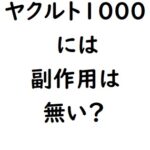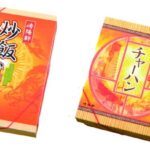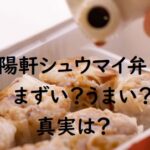ササニシキというお米の銘柄がありました。
今ではスーパーなどから姿を消してしまい今の若い人は知らないかもしれませんね。
今はコシヒカリ、秋田小町、ひとめぼれ などはスーパーなどの店頭で並んでしまがササニシキという銘柄が並ぶことは滅多になくなり消えてしました。
昭和生まれの方には馴染みだったササニシキは何故どうして消えてしまったのでしょうか?
ササニシキが消えた意外な理由がササニシキの特徴や歴史にあります。
ササニシキが消えた主な理由の原因が以下の4つ
- 冷害
- 品種改良
- 価格
- 嗜好
順に説明したいと思います。
そこから見えてくる時代と流行に翻弄されたササニシキが消えた理由意外な4つの理由が見えてきます。
目次
ササニシキが消えた4つの理由

一番の理由は品種改良でササニシキより簡単に生産が出来て、冷害にも病気にも強いお米が誕生したからですが、それ以外に様々な要因が重なり一気にササニシキの生産が減少してしまったからです。
その4つの理由をみていきましょう。
理由1・冷害による減少
冷害に強いと思われてきたササニシキが1993年の冷害にで大被害を受けたのです。
この被害によって他の品種のお米に乗り換える農家さんのササニシキ離れが進み作付面積が一気に減少したのが一つ目の理由です。
理由2・新たな品種改良のお米の登場
ササニシキよりも寒さに強く美味しい東北のお米が誕生しました。
それが「秋田こまち」であり「ひとめぼれ」でした。
もちろんササニシキも冷害に強い品種であったのですが、それよりも冷害に強い品種で病気にも強くうまみがあり人気もある品種が登場したことから、今まで作付の主流だったササニシキから取って代わってしまったのが2つ目の理由です。
誕生当時は画期的な品種改良品種だったササニシキも現代の品種改良されたお米と比べてしまうと、ササニシキは育成・管理が難しいとお米とされてしまいました。時代の流れて仕方のないことですね。
理由3・米価の下落
お米の自由化で海外のお米なども輸入されたり、また消費やのお米離れ、パン食の流行などもにも拍車がかかり、米価が値下げの傾向になりました。
そこで農家の方々はより単価の高いお米の品種のコシヒカリなどの銘柄に作付変更するようになったのもササニシキが減少した要因の大きな3つ目の理由です。
理由4・消費者の嗜好
若い世代に移り行くたびに、ご飯に対する嗜好も変わってきました。サッパリしたご飯よりも粘りが強くモチモチとした食感と甘いうまみが強いお米が好きな人が増えました。
それで、ササニシキの食味に人気が無くなったこと、売れなくなったことが消費者側から見た一番の理由ですね。
消えたササニシキの特徴と歴史

ひと昔の日本ではササニシキとコシヒカリが2大ブランドでした。
ササニシキは寒いところのお米というイメージがありますね。東のササニシキそして西のコシヒカリ。今ではコシヒカリの名産は新潟県魚沼産となってしまいましたが、コシヒカリは実は西日本が発祥なのです。
話しは少しそれましたがササニシキの歴史は昭和30年代まで遡ります。
ササニシキの誕生と歴史
東北の地は寒波などでお米の収穫が他の地域と比べて少なかったので、寒さに強く収穫量が多く美味しいお米をどうにかして作りたいと生まれました。
1963年(昭和28年)に東北の宮城県古川農業試験場で品種改良して寒さに強く収穫が多いお米として誕生したのがササニシキでした。
数年後には作付が始まり昭和60年の最後の頃にはお米の作付順位がコシヒカリの次に多い2位で東北の代表のお米でした。
しかし、今では全国的にも珍しい品種になり宮城のごく一部の農家さんで生産されているだけになりました。
ササニシキの食感や食味
コシヒカリなどのモッチリとした噛みごたえと甘みはありません。
どとらかというと
さっぱりして、粘り気が少なく、程よくお米がほぐれる喉越しが良い品種です。
その理由としては
アミロースが他のお米と比べて多いからです。
(例:コシヒカリ17%前後・ササニシキ20%前後)
お米の味を抑えてサッパリしているのでお寿司屋さんなどでは良く利用されていたお米でした。お寿司の具の味を引き立てるピッタリのお米でした。

今でも食材を引き立てるご飯のために
お寿司屋さんや高級レストランなどでは引き合いがあります。
しかし、生産量も少なく今では幻のお米と言われるほどになってしまいました。
【まとめ】ササニシキが消えた訳は時代の流れ

結論としては4つの原因をあげましたが、やはり一番の要因は農家さんがササニシキを生産しなくなった。それにつきますね。
ササニシキより簡単に生産できて、収穫も多い味も美味しいお米となれば必然的に現在主流の「ひとめぼれ」になってしまいますよね。
今のお米は北海道から九州まで色々な品種があり、多くの銘柄で販売されて楽天市場などでもネット販売されているお米の種類が多いこと。
その中でも目にするのはコシヒカリ、ヒトメボレやアキタコマチなど、つや姫や北海道産のお米「ゆめぴり」なども人気があります。
けれども、ササニシキはネット販売でも見かけるのは少ないですね。
平成27年度水稲の銘柄別検査
- 1位 コシヒカリ
- 2位 ひとめぼれ
- 3位 あきたこまち
- 4位 ヒノヒカリ
- 5位 ななつぼし
公益社団法人 米穀安定供給確保支援機構のR2年の「品種別作付動向」を見てみても一目瞭然です。ササニシキは上位20種にもランキングされていませんでした。
【R2年品種別作付割合上位20品種】(単位:%)
- コシヒカリ 33.7
- ひとめぼれ 9.1
- ヒノヒカリ 8.3
- あきたこまち 6.8
- ななつぼし 3.4
- はえぬき 2.8
- まっしぐら 2.5
- キヌヒカリ 1.9
- きぬむすめ 1.6
- ゆめぴりか 1.6
- あさひの夢 1.5
- こしいぶき 1.4
- つや姫 1.2
- 夢つくし 1.0
- ふさこがね 0.9
- あいちのかおり 0.9
- 天のつぶ 0.8
- あきさかり 0.7
- 彩のかがやき 0.7
- きらら397 0.7
主流はコシヒカリで全体の3割も占めて人気のお米5位でまでで半分以上の生産量になります。
楽天市場の白米や玄米などの販売ランキングでも2021年では30位にも入らなく圏外になっています。
Amazonの白米の販売ランキングでもササニシキは20以内にもない圏外ですね。
その理由としては手に入らないササニシキを業務用に業者や飲食店の方が購入しているのではないかと憶測しています。
どうしても、「甘味」「粘り」の2拍子がないと人気がでないのではササニシキは一般消費では売れなくなるのも仕方ないのかもしれません。
やはり時代の流れで、今の現代の品種の中では生産が難しい、一般受けが無いとなれば消えゆく運命なのかしれません。
しかし、今でも宮城の一部の農家さんが頑張って生産を続けています。
そんな農家さんを取材した記事の1部をご紹介します。
「ひとめぼれ」の存在が大きい。たとえ冷害がなかったとしても、遅かれ早かれ「ひとめぼれ」がササニシキに変わっていたと思う
引用:多摩川源流大学:君はササニシキを覚えているかい?
ここでも農家さんが話していますが品種改良の波には勝てませんね。
生活・家計がかかっているのですから・・・致し方ありません。
【補足】ササニシキの購入方法は?
需要が少ないので町中のスーパーなどでは店頭に置いているところは少ないのが現状です。
価格は他のお米と違って少々割高です。
5Kgほどで2500円前後で10Kgだと5000円程。
多くの人が食べているお米と比べると2割ほど高い感じですね。
詳しくは別記事で紹介しています。↓