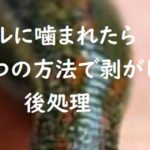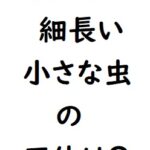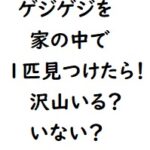この記事は約 4 分で読めます ( 約 1922 文字 )
- 更新
- 自然・生き物
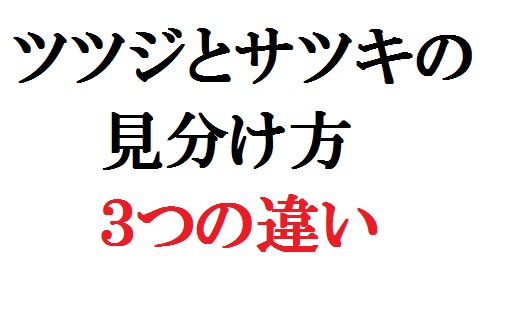
ツツジとサツキの花だけ見ると似ているので、確かに見間違い勘違いされますね。
街中で良くみかけるのはツツジです。
何故ならツツジは道路端の花壇に植えられていたり、街路樹の下に植えられたりしているからです。
それに対してサツキは盆栽などの鑑賞用に用いられたりしています。
また街路樹などには植えられることも少なく、自生のサツキは山中に多いのが特徴です。
私が小学生の頃には学校の帰り道でみんなと一緒にツツジの花を摘んで蜜を吸ったりしていたのを懐かしく思います。
ツツジとサツキの違いはあるのか?特徴はあるのか?見分け方などをご説明していきます。
ツツジとサツキの3つ違い
実はツツジもサツキも同じツツジ科ツツジ属の植物です。
ツツジはアジアに多く分布しています。
サツキは
どうりで、同じ仲間なので見た目が同じなんですね。
シャクナゲも同じ仲間に入っています。
ツツジ属の植物は低木から高木になる木です。
花は特徴のある漏斗型の花を4月から5月の春に枝先につけます。
同じ仲間なので見た目は同じように見えますが、特徴的なことを簡単な表にしてみました。
| ツツジ | サツキ | |
| 葉 | 大きくザラザラ | 小さくツルツル |
| 花 | 春4-5月 | 初夏5-6月 |
| 特徴 | 乾燥に強い | 湿気に強い・水際に生息 |
| その他 | 街路樹に人気 | 盆栽が人気 |
ツツジの3つの違い特徴

| 葉 |
|
| 花 |
|
| 生態 |
|
サツキの3つの違い特徴

| 葉 |
|
| 花 |
|
| 生態 |
|
日本皐月協同組合などの団体もある位ですから、サツキ盆栽は奥深いものなのでしょうね。
ツツジとサツキを3つの違いで簡単に見分ける方法

先ず咲く時期が違うのが特徴ですね。
- 4月から咲くのはツツジ
- 5月から咲くのはサツキ
- ツツジは葉や花が大きい(サツキより)
- サツキの方が葉も花も小さい(ツツジより)
- 葉っぱがザラザラしてればツツジ
- 葉っぱがルツツルしてればサツキ
ツツジとサツキの違い「まとめ」
サツキもツツジと同じツツジ科ツツジ属なので似ています。
ツツジは乾燥に強く花も綺麗なので道路の脇や生け垣、花壇など多くの市街地で見かけるのも納得しました。
サツキは湿気を好むために盆栽などに人気があることもわかりました。
最近は街路樹にはツツジが植わってないところが多くなったようなので気にしてました。
実は国で道路のツツジを植えないという方針があったようです。
「ツツジなどの低木とイチョウなどの高木を組み合わせた整備が求められている歩道の街路樹について、国土交通省は低木を植えなくてもいいようにする方針を固めた。」
なんともさみしいとも思いましたが、時代の流れかもしれませんね。
追記・ツツジの毒から名前の由来
ツツジの漢字は躑躅と書きますが、別の呼び方で「てきちょく」と読みます。
その意味は、足踏みすること。ためらうこと。です。
なぜ、その漢字がツツジなのでしょうか?
その由来にはツツジが毒を持っているからです。
中国の古典の中に、
子供の頃、花壇に植えられているツツジの多くの蜜を吸っていましたが、実はレンゲツツジという種類には毒性があります。
相当子供のころ蜜を吸っていましたが、毒のあるレンゲツツジでなかったのでしょう。
この頃道路でのツツジを見かけなくなりました。
中には市街地に植えられている場合もありますので、子供たちには安易に蜜を吸うことはやめるように促しましょう。
山間部によく自生していますが、鹿や野生動物が食べるのを避けているため群生して綺麗な真っ赤な花を咲かせているお花畑のような場所がありますので注意してください。
ワザと自らを目立たせて注意を促す植物の知恵ですね。