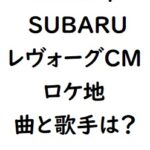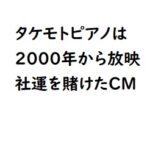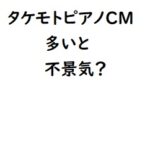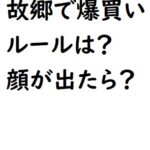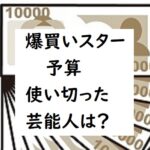この記事は約 4 分で読めます ( 約 2355 文字 )
- 更新
- テレビ
2019年5月2日二代目 和風総本家「旬の鎌倉を支える職人スペシャル」でとても綺麗な鎌倉彫が紹介されましたね。
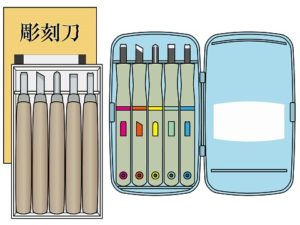
その鎌倉彫を一度自分で彫ってみたい、体験してみたい。そう思う多くに人がいると思いますが、実際に鎌倉まで行って体験するのは難しいと思いますね。
けれども、鎌倉彫の本家がある鎌倉以外でも鎌倉彫の体験や習得が出来る方法がありますのでご紹介いたします。
多くの鎌倉彫体験は鎌倉市内か、その周辺で体験できますが、都内でも体験できる場所もありますし、全国のHNKカルチャーセンターでも全国で定期的に開催されています。
もし、NHKカルチャーセンターが無いような場所でも市のカルチャーセンターなどでお調べになってみたください。
鎌倉彫が体験できる全国教室は?
R1年5月2日現在NHKカルチャーセンターでは17件が鎌倉彫の教室に登録されています。
検索窓に「鎌倉彫」で検索するとでてきます。
ただ残念なことに人気があるのか、キャンセル待ちの処も多数あります。
1回限りの数時間で終了するようなコースではなくて定期コース。
金額も1万円から4万円までと結構金額がかかります。
実際に彫でりなく塗りにお金にかかります。
東京・青山教室では3コース。
東京・町田教室では1つ
他にも
- 東京・八王子教室
- 横浜ランドマーク教室
- 千葉教室
- 埼玉・さいたまアリーナ教室
- 埼玉・川越教室
- 埼玉・宇都宮教室
- 群馬・前橋教室
- 静岡・浜松教室
- 大阪・梅田教室
- 兵庫・神戸教室
- 愛媛・松山教室
などなど全国各地に教室があります。
鎌倉彫の体験ができる東京都内の教室は?
本部は鎌倉にありますが、都内など数か所で一日体験(予約)ができます。
教室 ※詳しくは教室一覧
神奈川3教室
東京5教室
| 料金 | 1500円(材料、彫刻刀レンタル、受講料込み) |
| 時間 | 3時間 |
| 定員 | 2名まで |
| 日時 | 平日 10~13時:14~17時 日曜(第2・4) 10~13時 |
他には8寸丸盆体験 2000円コースもありますが、そのコースは教室に入会を検討することが条件です。
また、鎌倉彫の体験は「彫」までで、「塗り」を希望される方は別途対応です。
- 鎌倉市御成町11-29
- 鎌倉彫教室鎌陽洞
- 0467-22-5550
鎌倉彫りの体験ができる本場・鎌倉市内の教室は?
やはり本場の鎌倉を中心に実技も含めて多くの鎌倉彫の体験コースが存在しています。
料金も3000円ほどで手軽に体験できます。
主な2つの体験教室を紹介します。
鎌倉彫資料館
- 鎌倉彫資料館
- 〒248-0006鎌倉市小町2-15-13
- 電話:0467-25-1502
公式サイト:http://kamakuraborikaikan.jp/museum/
| 料金 | Aコース:小中学生1,300円 Bコース:小中学生2,700円、大人3,200円 (材料費及び鎌倉彫資料館入館料を含む) |
| 時間 | 2時間コース |
| 日時 | 第1・3日曜日10時00分~と13時00分~ 第2・4土曜日10時00分~と13時00分~ 第1・2・3・4金曜日10時00分~と13時00分~ |
| 木地 | A.9cm角コースター
B.17cm丸盆(大人はBのみ) |
伝統鎌倉彫事業協同組合
- 鎌倉彫工芸館
- 〒248-0014鎌倉市由比ガ浜3-4-7
- 電話:0467-23-0154〕
公式サイト:https://www.kamakurabori-kougeikan.jp/
| 料金 | 児童 2,000円
一般 2,500円 材料費別途 |
| 時間 | 2時間コース |
| 日時 | 日時 火曜日~土曜日:9時00分~16時00分 日曜日・祝日:11時00分~16時00分 |
| 木地 | びん敷、丸盆、コースターなど |
鎌倉彫の体験は通信教育でできるのか?
残念なことに鎌倉彫の通信教育はありませんでした。
本などは沢山紹介されていますが、通信教育だとしても鎌倉彫は紙面などでは伝えきれない実技での実習がメインになるので、本と同じ内容でしたら意味が無くなるのでやはりないのでしょうね。
【まとめ】「鎌倉彫り」の体験できる教室は少ない
通信教育では鎌倉彫は体験できないので直接に教室に参加しなければなりません。
地方の方はカルチャーセンターなどのご利用をお勧めします。
また関東近郊の方であれば最初の体験は直接に鎌倉市まで足を延ばしで本場の鎌倉彫を体験されることをお勧めします。
何故なら鎌倉市で体験することにより、多くの作品とも触れ合うこともできますし、市中のお土産屋さんや美術館等でも本物の鎌倉彫に出会うことができるからです。
是非鎌倉で本場の鎌倉彫をご堪能してみてください。
追記:鎌倉彫の歴史・現在の状況について
鎌倉彫の由来は
約800年前の鎌倉時代に中国から禅宗(日本では臨済宗や曹洞宗)が伝わります。
その禅宗とともに仏師も渡来して仏具などを作っり、それが木地に模様を薄く彫刻してそれに直接黒漆を塗り、最後に朱や青、黄色などの色漆を重ねて磨き上げる鎌倉の工芸品となり鎌倉彫が伝えられています。
その資格するには大変な下地が必要で、なんと一級では実務経験15年以上で大学の彫刻、工芸学科などを卒業して実務経験が11年以上あることが前提になっています。
800年以上にわたり受け継げられている技術は凄いものだと感じました。
また、そんな技術を後世に伝えるためにも、気軽に鎌倉彫が触れられる場所や機会を増やしていくべきだと痛感いたしました。
今は鎌倉中心でしか体験できませんが、今はネットの世界なので多くの人にネットで浸透して拡散して広めていく努力も必要だと思わされました。